『みどりのゆび』
モーリス・ドリュオン作
安東次男訳
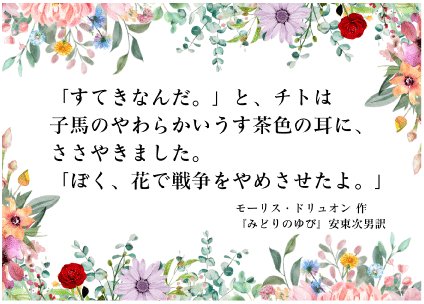
どんな場所でも、たちどころに種を芽吹かせ、花を咲かせるふしぎな力を持った少年チトの物語です。チトはそのとくべつな能力で、訪れた先々に花を咲かせていき、町全体を緑に変え、とうとう戦争までとめてしまいます。花で戦争をやめさせるなんて、「なんて荒唐無稽なお伽話」と笑ってしまうか、それとも、その奇跡に「真理がこめられている作品」と感じるか、あなたはどちらでしょうか。
物語は、生まれたばかりのチトが、名前をつけてもらうところからはじまります。「とくべつの役目をおびてこの地球に生まれ、とくべつにやらなければならない仕事」を持つために、「どこの国にも見当たらない」名前で呼ばれるようになった子ども――と暗示されるのがチトです。金髪に大きな青い目、つやつやのばらいろのほおで、だれからも愛される少年に育ったチトに、鉄砲の商人で大金持ちのおとうさんは、こう語ります。
「チトや、うちの商売はよい商売だよ。雨がさは、おてんきがよいとだれも買わない。むぎわらぼうしは、雨のおおい夏なら店さきにおかれっぱなしだ。しかし鉄砲には、そんなしんぱいはいらない。おてんきにかかわりなしに売れるからね。」
はじまりで暗示されたとおり、チトは成長するうちに「ほかの子どもと同じではない」ことがあきらかになっていきます。学校には行かずに学ぶため、最初に受けたのは庭と土の授業でした。そこで出会った先生は、「ひげさん」と呼ばれるみごとな白いひげをはやした庭師のムスターシュです。花と語り合う専門家の彼は、チトが「みどりのおやゆび」――触れればどこにでも花を咲かせる、おどろくべき才能を持っていることを即座に見抜きます。そして、その才能を「だまっていなさい」と、秘密にしておくよう助言します。
ところがチトはその後、町の規律を学ぶために訪れた刑務所、貧民街、病院を、次々に花と緑でいっぱいにして、町じゅうにおどろきとさわぎと興奮をもたらしていきます。以下は、生まれつき病身で歩けない女の子に、チトが起こした奇跡の場面です。
ちいさな女の子は、花園のなかで目がさめて、にこにこしていました。
夜のあいだに、テーブルのまわりにスイセンがさいていたのです。カラスムギが波をうっていました。それから、チトが心をこめてつくった、すばらしいバラの花が、たえまなく変化し、葉をひらいたり芽をふいたり、まくらにそって、ベッドのあたまにはいのぼっていました。女の子はもう天井をみつめてはいませんでした。うっとりと花をながめていました。
その夕方、女の子のあしはうごきはじめました。生きていることが、この子には、たのしくなったのです。
色とりどりの花たちと、生きる希望を見いだした女の子の笑顔、なんて心おどる描写でしょう。チトはこの調子で、町の動物園までいきいきとした場所にかえてしまいます。「みどりのゆび」の真骨頂に読者は拍手喝采ですが、作中のおとなたちは、予測できない出来事の連続にがまんできずに混乱します。そこへ解決策を提案したのは、議会での信頼厚く、決断力のあるチトの「おとうさん」氏でした。自分の息子のしわざであるとも知らずに、人々にこう呼びかけます。
「みなさん、はらをたてるのはよくない。のみならず、理解できないからといってはらをたてるのは、いつでもきけんです。われわれのうちには、いかなるわけによってあれらの花がとつぜんさいたのか、知っているものはひとりもいません。しかるにみなさんは、花をむしれとおっしゃる。しかしあすになったらどこにはえるか、おわかりになっているでしょうか? またいっぽうからかんがえますと、これらの花はわたくしたちをこまらせるよりも、むしろ役に立ってくれるほうが多いのであります。そのことは、みとめなければなりません。げんに、囚人はひとりとして逃亡しません。貧民街はいまや繁栄しつつあります。また病院にいるこどもたちは、みんななおっております。それなのに、なぜいらいらするのです? みなさん、花をいかしてつかいましょう、そして今日のできごとのあとを王よりも、むしろ一歩さきをみて、ことをはかろうではありませんか。」
この提案は「ばんざい」の声で受け入れられ、町は≪花の町ミルポワル≫という名前になりました。ところが、町全体が変わっても、それでも、チトの疑問と行動はとまりません。「ぼく、世の中ってもっともっとよくすることができると思うよ。」ムスターシュから「戦争」の真実を学び、おとうさんの工場を訪ねたチトはとうとう、武器づくりという「おそろしい商売」の矛盾に気づくのです。そこでチトがとった行動と、その結末は……圧巻のひと言です。モノクロでも香るように美しいジャクリーヌ・デュエームの挿絵も相まって、「せんそうはんたいを花で」あざやかに訴えかけてくるその場面はぜひ、本文で味わっていただければと思います。
戦争がとまってむかえた静かな朝、武器商人だった「おとうさん」氏の嘆きは、たいへんなものでした。「破滅だ! 恥だ!」「ああ! わたしの大砲が……あのうつくしい大砲が……」と叫びがつづきました。けれども、「花の種をまいたのは、ぼくです」というチトの告白を受けて、たっぷり1週間もしんけんに考えこんだ末に、ひとつの答えにたどりつきます。
「どうやら、わたしたちがやってきたことは、むじゅんしていたようだ。」とおとうさんはおかあさんにいいました。「いっぽうで最上の大砲をつくり、もういっぽうでチトをしあわせなこどもにそだてたんだからね。このふたつは両立しない。」
なによりも子どもの未来を大切に考えたうえで、大砲工場をつくりかえることにする「おとうさん」氏の決断は見事です。「英雄的で、感動的」と形容されるこの言動と人物造形には、人間の理性と良心への信頼が託されているように感じられてなりません。(現代の政治家たちにも見習ってほしいほど!)こうしてチトの念願は叶えられて、めでたしめでたしかと思いきや……物語のラストには、読者の胸を突く大きな衝撃が待っています。
初めて読んだ小学生のとき、「まさか、こんな終わり方って……」とショックを受けたことをおぼえています。小さなチトに感情移入して、花たちの活躍と劇的な町の変化にわくわくして、おとなたちの混乱ぶりが痛快で、心から楽しんで読み進めたラストには、ハッピーエンドがあることを信じていました。それなのに……こんな哀しみが残る終わりはあんまりだ、と本を閉じたまま、再読することも避けていました。
けれども、おとなになって再び読み返し、作者とその背景を調べるうちに、気づいたことがあります。この結末は、読者の期待を裏切ることさえ、意図的なものだったのではないかと。作者はあえて「めでたしめでたし」ではない物語の終わり方で、忘れられない種を、読者にのこそうとしたのではないでしょうか。チトが起こす奇跡のように、すぐに花咲くことはなくとも、いつかおとなになったときに芽吹く種を、ひそやかに深く、読者の心に植え付けることにこそ、作者のねらいがあったのではないか、と。
作者のモーリス・ドリュオンは1918年にフランスのパリに生まれ、第2次世界大戦に出征した経験もある作家です。フランスがナチスに占領された際には、もともとロシア語で伝わっていた「パルチザンの歌」(「ラ・マルセイエーズ」に次ぐフランスの第二国歌)を訳して、民衆に抵抗を呼びかけた人としても知られています。『大家族』に始まる三部作『人間の終末』が高い評価を受けて、フランスの最高学術機関であるアカデミーフランセーズのメンバーに選出され、一時は文化大臣も務めました。「みどりのゆび」は、そんな経歴を持つ作家が、自ら経験した戦争のテーマに取り組んだ、とくべつな作品でもありました。そうした背景を知ればなおさら、この物語は「単なる反戦童話」――安易な「めでたしめでたし」で終われたはずがないと思えます。
「みどりのゆび」の主人公チトの視点は、あくまでも無邪気な子どものそれを装って描かれていますが、まっすぐに物事の本質を見抜くことで、おとなたちに戦争の矛盾、本質的な問いを投げかけていきます。そして、そのふしぎな力で町を変え、戦争をとめ、人々の心をゆさぶる奇跡をのこして去っていきます。読後にとりのこされた読者は、その哀しみの種を飲みこんだままおとなになり、あるとき、そこに隠されたメッセージがあることに気づくのです。
それは、チトのいない現実、戦争の続く世界で、「みどりのゆび」の奇跡を待つことはできないということ。けれども、「みどりのゆび」を持たない読者にも、種を蒔くことはできるということです。私もあなたも、チトに代わって平和の種を蒔き、しんぼうづよくそだてることで、花を咲かせることはできる。現実に生きる読者は、平和のための行動を起こすことができる。「おとうさん」氏が、チトのために決断したように、未来の子どもたちのために。小さなチトがしたように、勇気をもって。
出征して戦地を体験したドリュオンが、小さな少年と花に託した物語の種から私が受けとったのは、そうしたメッセージでした。そして、日々ふえていく戦争のニュースに耐えきれず、手がかりをさがしはじめるうちに、それぞれの場で、それぞれの形で平和の種蒔きを実践する、すばらしい先輩たちに出会いました。その出会いにも勇気づけられ、いまこそ行動を起こそうと始めたのが、いまご覧いただいているこのサイト――Peace & Plant Libraryです。
「花で戦争をとめてしまうなんて、荒唐無稽なお伽話」だと笑いますか? この物語に託された信頼と希望、チトからもらった種が、ひとりでも多くの人に届きますように願いながら、この紹介文を綴っています。微力ながらこれからも、植物と本の力を借りて、情報を発信していきます。あなたも「種蒔く友」のひとりになってくれたら、とてもうれしいです。
(2024年9月)
合わせて読みたい本
『わたげちゃん』
ポール・エリュアール作
ジャクリーヌ・デュエム絵
薩摩忠訳
ドリュオンとおなじくナチス・ド�イツへの抵抗運動に参加した詩人・エリュアールが文を、「みどりのゆび」の挿絵を描いたジャクリーヌ・デュエムが絵を担当した絵本です。小鳥のように空をとぶことを夢みるふしぎな女の子・わたげちゃんの冒険を、美しいカラーイラストで楽しむことができます。こちらはハッピーエンドなのでご安心を。
